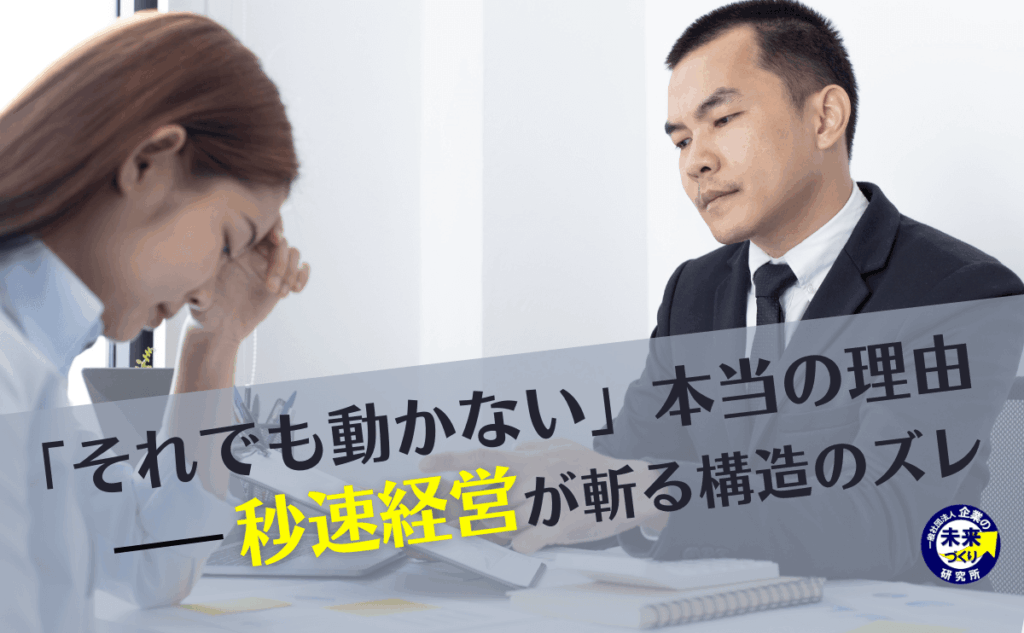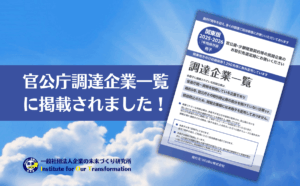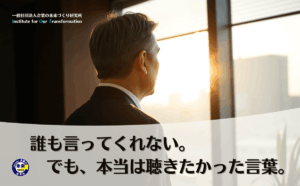「それでも動かない」本当の理由──秒速経営が斬る構造ズレ
はじめに
「会議で決めたはずなのに、現場がまったく動いていない」 「ちゃんと指示したのに、なぜやらないんだ?」
これは多くの経営者・管理職が感じる“あるある”の悩みです。 中には「部下の意識が低い」「自分がもっと強く言えば良かった」と自責したり、 逆に「やる気がないなら辞めてもらって構わない」と突き放すケースもあるかもしれません。
でも、少し視点を変えて見てみましょう。
「決まったのに動かない」現象の背景には、“意識”や“やる気”の問題ではなく、組織に潜む3つの“構造的なズレ”があるのです。
「問題は“指示が弱い”から」と思っていませんか?
行動が伴わないとき、多くの上司がまず思うのは「もっと強く伝えるべきだった」という反省です。
確かに、伝達力やリーダーシップは重要です。 しかし、どれだけ明確に、強く指示を出しても、構造がズレていれば人は動きません。
それは、どんなにエンジンの性能が高くても、タイヤが空回りしていれば前に進まないのと同じです。
問題は、もっと根本にあります。
秒速経営の視点:動かない本当の原因は「3つの構造ズレ」
秒速経営プログラムでは、企業が“止まる”原因を、「個人の意識」ではなく組織構造と関係性の中にあるズレとして捉えます。
① ベクトルのズレ(目指す方向が共有されていない)
現場と経営層で“言葉では同意している”のに、行動がバラバラになるのは、目指しているゴールや基準が共有されていないからです。
たとえば「お客様満足を高める」と言っても、営業は売上、開発は品質、サポートは対応スピードを優先するなど、現場ごとに“満足”の定義がズレている場合があります。
そのまま進めば、当然バラバラになります。
② 関係性の摩耗(信頼と対話が機能していない)
「聞いてない」「言ったのに」「あの人が勝手に決めた」── これらは関係性の摩耗による“協働の劣化”のサインです。
単なる伝達や報告ではなく、相手の背景や想いを聴き合える関係性があって初めて、決定は“納得”に変わり、行動へとつながります。
関係性が壊れていると、指示は“押しつけ”に聞こえてしまうのです。
③ 思考プロセスの不一致(考え方のステージがズレている)
経営陣が“未来を描いて挑戦したい”と考えていても、現場は“今の仕事を回すことで手一杯”という場合、話がまったく噛み合いません。
どの思考レベルで会話しているのか(視座・時間軸・優先軸)がズレていると、話し合いが平行線になり、決定が“実行不能”になってしまうのです。
「正しいことを言ってるのに、なぜ動かないのか?」
これは管理職の多くが感じる“もどかしさ”です。
でも実は、「正しさ」は人を動かしません。
なぜなら、人は”納得”しなければ行動に移さないからです。
上司や経営者がどれだけ「ロジック的に正しい」判断を下しても、それが部下の「自分ゴト」になっていなければ、行動にはつながりません。
つまり、必要なのは“押しつける説得”ではなく、「納得の通路」を設計することです。
秒速経営の出発点:「納得の土台」をつくること
秒速経営では、対話と意思決定の土台を丁寧に整えることで、行動につながる納得のプロセスを設計します。
その際には、少人数での対話から全体へと段階的に展開する独自の進め方を採用しており、立場や遠慮によって本音が出づらい状況でも、無理なく“自分ゴト化”が促されていきます。
このプロセスを通じて、「決定が自分ゴトになる」構造を自然に組み込んでいくことが可能になります。
結果的に、それが止まっていた組織を再起動させる起点となるのです。
おわりに:「動かない」は誰かのせいじゃない
人が動かないとき、つい誰かのせいにしたくなります。
「現場がダメだ」「上司が弱い」──
でも、そうとは限りません。
止まっているのは、人ではなく“構造”であることが多いのです。
その構造を、問いと関係性によって整え直す。 それが、秒速経営プログラムが担う大きな役割のひとつです。
「組織は人が動かす」とよく言われますが、 「人が動ける構造」を整えることこそが、組織の未来を変えていく鍵だと、私たちは考えています。
あなたの組織が、動き出すきっかけとなりますように。