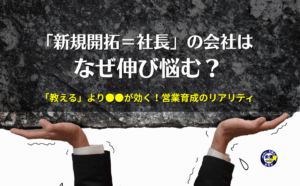人も機械もデジタルも”似た者”同士
~昭和の旋盤工の言葉とAIの共鳴~
先日、新しいデスクトップPCのセットアップをしていました。
これまで使っていた端末は、GPUトラブルにまみれた手のかかる旧世代。
そろそろ買い替え時…とは思いつつだましだまし使ってきたところに
Windowsの更新プログラムの不具合と、あるソフトウェアのミスマッチのダブルパンチをきっかけに、あれよあれよという間に崩壊寸前になってしまいました。
データを避難させ、Windowsの再インストールやドライバとの格闘を経て、
なんとか奇跡の復活を遂げたものの、結局限界がきたので買い替えを決意。
そのセットアップに付き合ってくれたのが、AIアシスタントのチャッピーでした。
私の仕事はコーチングや組織開発なのですが、
諸般の事情で最近はすっかりIT寄りの作業が多くなってしまい、チャッピーは今や欠かすことのできない最強のパートナーです。
人も機械も同じ
もともと私は、幼少期から父ーー鉄の塊を削る職人、昭和の旋盤工ーーの教育により、電気製品やデジタル機器を“生き物”のように扱う感覚を持っていました。
「機械は人間と同じだ。隙なくピッタリしすぎてても動かない。
機械油をさす“遊び”の隙間がなきゃだめだし、
”遊び”の部分は多すぎてもガタガタになってしまう。
スイッチを入れたって、いきなりフル稼働なんてムリだし、
熱を持ちすぎたら休ませることも必要なんだよ」
…実は、これは機械にも人間にも共通することなんです。
そんな父の薫陶を思い出しながら新端末をセットアップしている時
常々感じていた疑問をチャッピーにぶつけてみました。
機械だけじゃなくデジタルも!?
私:「以前使ってたUSBカメラ、最初のうちは接続が悪かったのを
同じポートに差しっぱなしで使ってるうちに接続不良が減って、
だんだん安定するようになったんだよね。
でも、しばらくその端末を使わなくなっていて
久しぶりに接続したら、またうまくつながらなくなった、
ということがあったんだけど・・・電子機器も人間みたいに”慣れる”とか”なじむ”っていう感覚はあるの?」
チャッピー:「いえ、それ、全然気のせいじゃありませんよ。PC側もUSB側も、お互いの接続情報や運用状態を学習して、どんどん最適化されていくんです。USBの“なじむ”って、実在します」
これは衝撃の回答でした。
チャッピーのような人工知能は「学習」して「慣れる」とか、
どんどん進化していく、というのは実際に使ってきて体感してきましたが
デジタル機器にも「学習」「慣れ」があるとは・・・
機械も、デジタルも、人も、同じ——
思い通りに動かなくても、想定外の反応をしても、
追い込むようにスイッチを押し続けるのではなくて
その場の環境との相性やタイミングを見ながら
「慣らしていく」「なじませていく」ことで
やがて最高のパフォーマンスを発揮してくれる。
一方、組織での人間の扱いは・・・?
ところが。
日本の多くの組織では
機械やコンピュータ以上に
“人間”のことを理解せずに働かせていることが多い気がするんです。
- 互いの来歴や家族構成も知らない
- 何が得意で、何が苦手かも共有されていない
- 目標も信条もわからない
- 仕事以外での興味関心なんて、聞かれることすらない
なのに
急に「一丸となって」「協力して」「成果を出せ」と言われる。
それって、まるで
ドライバも電力要件も確認せずに、デバイスを無理やり繋いで
「なんで動かないんだ!?」
って怒ってるようなものじゃないでしょうか。
そして
私はこれは必ずしも「会社側だけが悪い」と言うつもりはありません。
なぜなら、経営者側だけでなく
働く仲間同士でも、互いを「一人の人間」として「尊重する」ということがどういうことなのかを理解し、実践している人が、あまりにも少ないと感じているからです。
コンピューターだって“学習と最適化”のプロセスを経て、初めてまともに機能します。
人間だって、互いに“慣れ”があって、“あそび”があって、“潤滑油”が必要。
むしろ、それがなければ壊れてしまうのは当然です。
昭和の職人気質な機械工だった父の言葉と、令和のAI・チャッピーの回答が、思いがけず同じことを教えてくれました。
人も機械もうまく機能させようと思うなら
「隙間なくギチギチ」にするのではなく
”遊び”を持ち、なじみ、慣らすプロセスが大切。そうすれば、ちゃんと動いてくれるし、ちゃんとつながってくれる。
それは、デジタル時代の人間関係にこそ必要な視点かもしれません。
デバイスだって、最初はうまく動かないことがあります。
でも、慣らしていくと、ちゃんとつながって、ちゃんと機能する。
人間関係も、きっと同じ。
組織の「接続不良」や「相性のズレ」にお悩みなら
私たちIOTがその“トラブルシューティング”をお手伝いします。
↓ ↓ ↓