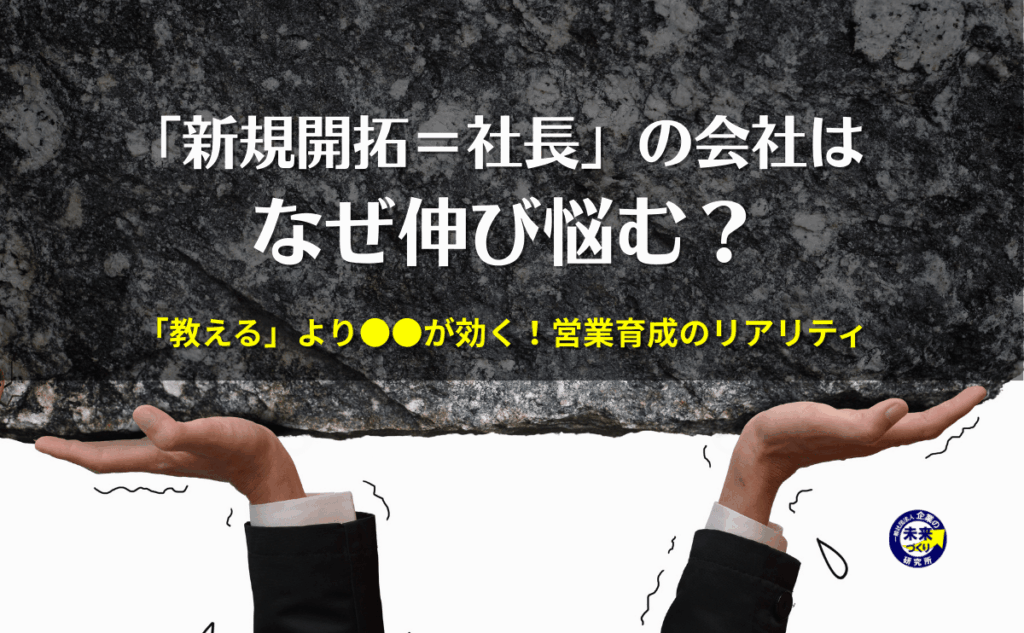「新規開拓=社長」の会社は、なぜ伸び悩むのか?
— 教える < 考えさせる、営業育成のリアリティ —
はじめに:分担は“明確”なのに、未来が重たい
100~300名規模の企業でよく聞くのが「新規顧客開拓は社長、既存は社員」。
一見、合理的です。
立ち上がりは速く、社長の突破力も活きる。
でも、ふと立ち止まると見えてきます。
「この体制、組織として本当に強いのか?」
一点集中の副作用:社長に乗る“未来の全部”
社長のカレンダーは、アポ・展示会・夜の会食でギッシリ。
売上の“未来”がほぼ社長の手に集約され、倒れたら止まるリスクが高い。
さらに入口が一本だと、顧客の多様なニーズを取りこぼす。
既存担当の社員は“維持”の達人になっていく一方で、
拡張の設計は育ちにくい——結果、売上は横ばい、利益は削られ、現場の自信も育たない。
“権限委譲すれば解決”の罠
「じゃあ権限委譲だ」で役割表を整える会社は多いですが、ここに第二の壁。
“やり方が分からない人には、役割だけ渡しても動けない”
しかも、社長の暗黙知(仮説力・即興性・広角視点)を丸ごとトレースさせようとしても、たいていは劣化版のコピーになります。
だからこそ、権限委譲“だけ”では回らないのです。
カギは「教える<考えさせる」
必要なのは、模範解答の伝授ではなく、仮説→実行→観測→言語化を自力で回せる“思考の筋力”づくり。
IOTが重視するのは、良質な問いが循環する場を継続的に設計すること。
営業会議の空気を変えるのは、こんな対話です。
- 「今日の新規、表の困りごとは何で、裏の困りごとは何っぽかった?」
- 「それを確かめる1枚の仮説メモを書ける?」
- 「入口を3つ用意しよう。価格/スピード/運用負担、どれから入る?」
ポイントは・・・
社長がすぐに答えを与えないこと。
社長と社員とでは、お客様にとっての「意味」も「見え方」も違う・・・つまり全く同じようにはいきません。
問いの設計と検証の型だけを渡し、本人の言葉で再現させる。
勝ち負けの評価よりも、どこで観測がズレたかを丁寧にほどく。
これで社員は「社長の代替」ではなく、自分のやり方で勝てる営業になります。
放置ではなく“設計”:小さく試し、短く振り返る
「考えさせる=放置」ではありません。
小さな新規(試せるサイズ)と短い振り返りをセットで回す。
たとえ少額でも
仮説→実行→観測→言語化の1サイクルを週単位で回すと、入口のバリエーションが増えます。
価格で入れないなら、導入手間ミニマムという入口は?
予算承認が重いなら、通りやすい費目設計は?
——ここから新たな切り口が立ち上がるのです。
社長の役割は「ストライカー」から「設計者」へ
最前線の一騎当千から、入口を増やす設計者にスイッチ。
誰が/どの仮説で/どの顧客群に/どの順で当たるのか。
入口が3本あれば、一本が詰まっても全体は止まりません。
不在リスクは下がり、社員の自尊心は上がり、会社は速く前進できるようになります。
なぜ“社外のプロ”を入れると早いのか
実は、ここが実務の肝。
マインドセットが絡む育成を社長が直接やると、善意でも圧になることがある。
受け手が「評価される怖さ」を感じ、本音や仮説が出にくいのです。
実はこのほかにも大きなデメリットがあるのですが、それについてはまた後日、解説しますね。
第三者(=社外ファシリテーター)が間に入り、
心理的安全性と対話の型を設計すると、社員も社長も客観と冷静を取り戻すことができます。
IOTでは、組織の“詰まり所”を見える化するチェックや、
質問カード型のワークを使いながら“考えさせる”を習慣化します。
結果として、社長依存の新規開拓から、チームで入口を増やす営業へ移行できます。
「早い社長」より「速い組織」
「社長=新規開拓」は創業期の強い矢でした。
けれど、同じ矢ばかり引くほど、組織の射程は短くなる。
教える < 考えさせる
問いが回り、仮説が回り、言葉が増える現場は、入口を増やし、未来の売上を手繰り寄せる力がグンと上がります。
社長の肩から荷が降り、空いた手で次の山へ。
そこから、会社の速度が一段上がります。
無料Zoom相談(30分):御社の“新規の詰まり所”を一緒に可視化します。
👉 お申込み:https://x.gd/FO4tr
秒速経営プログラム(企業研修):対話設計×実装で「教える<考えさせる」を社内に定着。
👉 導入の流れ・事例はサイト内ページへ
関連コラム:「“報連相”の順番、逆じゃない?」ほか会議シリーズ