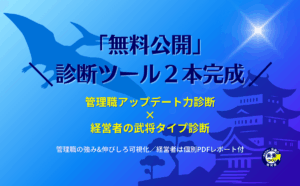「評価モード」の罠——ベテラン上司が引き起こす”誤作動”と、QQが担う安全装置
「聞く技術」の講座や書籍が世の中に溢れていても、うまく機能しない現場があります。
理由はシンプル。耳のモードが違うからです。
相手の話を“採点しながら”聞く耳、あるいは“好奇心で”聞く耳。
聞く技術を語る本の中には、技術と心構えを両輪で説くものが多く、読んでいる時は納得するものの、実践するのは難しく、やってる”つもり”止まりになってしまいがち。
そこで私たちが提唱するのは、もっとシンプルなこと――技術の前に、耳そのものの切り替え・更新です。
相手を「評価する」のは上司という役割の宿命ではありますが、時には、それを引っ込める必要があるんです。
私たちは研修で、まず“評価されずに話す経験”を、参加者全員で共有します。
すると、表情が変わる。声の質が変わる。
沈黙が怖くなくなる。――その瞬間、耳のモードが切り替わるのを、目の前で見てきました。
評価モードが生む三つの誤作動
① 正解当て現象
常に評価モードで接する上司の部下には、上司が喜びそうな答えを探すことがクセになります。
その弊害は、思考が保守化するだけではありません。これが習慣化すると「自分の考え」そのものが削られていくのです。「あなたはどう思う?」「あなたの考えは?」と問われ、真顔で「わかりません」。
冗談ではなく、現場で何度も見てきた光景です。
これが深刻化すると、自分で自分の気持ちまでわからなくなる…メンタルダウンへ突入、ということにもなりかねません。
② 関係の幻想
「アイツは○○なヤツだ」「話が分かるやつだ」――ラベルが増えるほど、本音は遠のきます。
もしあなたの、その“わかっている”が誤解だったら?合っていたとしても、人間は成長・変化する生き物なので、いつまでも「同じまま」とは限りません。
誤解の固定化が重なると、時間差で効いてくる関係性の歪み、ズレの拡大再生産が進みます。
③ 隠ぺいの引き金
厳しい評価の耳に向き合う部下や取引先は、不都合なことを語らなくなります。
そしてある日、問題は遅れて一気に表面化します。コンプラ問題の引き金、元凶はこの評価モードの耳だと言っても過言ではないでしょう。
ここまで言うと「評価モード=悪」のように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。
“常時オン”が危ういだけ。使い分けの不在が問題なのです。
「お世辞耐性」は誰にもない
人は、お世辞に弱い生き物です。優秀か凡人か、善人か悪人かも関係ありません。
私が会社員時代にとてもお世話になった、ある上司を思い出します。
彼は、世界各地でプロジェクトを手掛けるなど、経験豊富で柔軟性のある、話の分かる人でした。
ところが、彼は、隣の部署のパワハラ部長——目上にはへつらい、下には厳しい——の実態だけは見抜けていませんでした。その問題のパワハラ部長は、自分より”下”の人間には横暴なふるまいでしたが、自分の評価に影響する相手には徹底的に”聞こえのいい話”しかしない人でした。なので、私の上司に対しても自分の”イイ面”しか見せていなかった。
私はある時、その認識のズレに気づいたものの、私からそれを言うと「告げ口」になってしまうし、自分の仕事とは関係なかったので、敢えて上司には何も伝えませんでした。
ピラミッド型の組織では、見下ろす側からの景色と、見上げる側からの景色はまったく違います。
上からは外面、下からはその内側が透けて見えるという構造なのです。
だからこそ組織には、個人の善意や力量に頼らない対話の設計、評価が入りにくい場の設計が必要なんです。
耳にかかる偏りを、仕組みで外し、仕組みで守る。それには、人間を理解した上での設計が大切です。
IOTの QQ研修(QuestionQuest™) が担う役割
QQは、相手の話を採点しようのない仕組みになっています。
同じテーマでも答え方は一つではないこと、表現が似ていてもその背景や意味合いが違うこと、その違いに気づくための舞台装置がQuestionQuest™というカードゲームを使ったワークです。
QQ研修では、ベテラン・若手を問わず「楽しいのに脳が疲れた」という感想を、よくいただきます。
なぜそんなことが起こるのか?――カードのお題が想定外だからです。
話し手は、職場で習慣化した“求められる理想の答え”ではなく、自分の内側を探る必要がある。
正解当てに慣れた人ほど、最初は苦労します。
聞き手に回った時も同じで、いつもの“評価の耳”では捉えきれないため、脳の回路を入れ替える必要がある。
「脳が疲れた」という人ほど「硬直した思考パターン」だったとも言えますが、ポジティブに言うならば、耳のモードが“好奇心”へ切り替わったサインです。
QQ研修では、そんな風に脳の筋肉痛を感じながら体感としての納得が得られるというワケです。
なお、QQはHow Toや理屈ではありません。順序と安全性、体験がすべてです。
ワーク(ゲーム)自体がとても楽しいので、一度体験すると「ぜひ私もやりたい」と仰る方も多いのですが
断片を真似ただけでは、別の評価軸を生み、心理的負荷を残し、効果を逆転させてしまいます。
だからこそ、目的・対象・時間・関係性に合わせて設計すること・・・現場仕様への翻訳が重要なのです。
私たちが一貫してやっていることは、たった一つ。耳の更新を、設計で支えること。
「評価モード」は、いわゆる優秀な上司や、ベテラン上司ほど陥る経験の罠です。
人を責めずに「仕組み」で守るのが私たちのやり方です。
多様性が“生産性”に変わる瞬間——参加者の能力を引き出しながら進める会議——風通しの良い風土——それらの出発点は、「耳」。
たったそれだけの違いかもしれません。
耳のモードを切り替える安全装置にもなる、そしてどんな人でも、イヤでも「評価モード」になりようがない仕掛けの詰まったQuestionQuest研修。
「それってどういうこと?」
「ウチの頭の固いアノ人でも大丈夫?」
「メンバーの対立や不和もなんとかなるの?」
そんな興味・疑問のある方はぜひ個別相談申込フォームからお問い合わせください。
↓ ↓ ↓
💎個別相談申込/お問合せフォーム➡ https://x.gd/FO4tr
💎実地レポはこちら(中小企業診断士・法定講習でのQQ体験)
詳細はコチラ➡ https://ourdx-mtg.com/2025/09/20/qq-diversity-to-productivity/
💎ベテラン上司のセルフチェック(無料)アプリ
🦖管理職のアップデート力診断
🏯経営者の武将タイプ診断
➡https://ourdx-mtg.com/shindan/