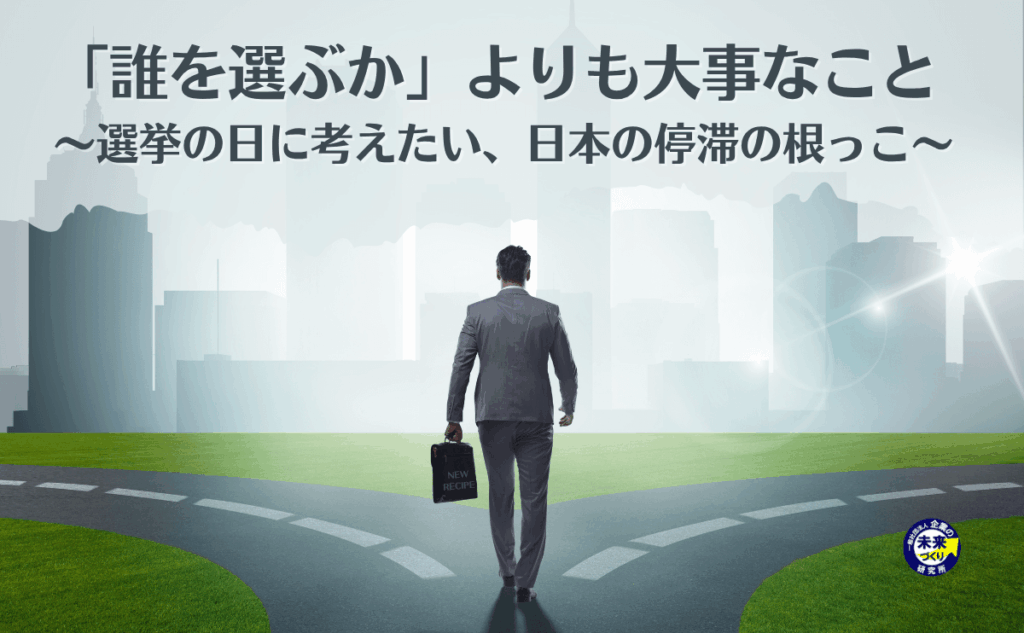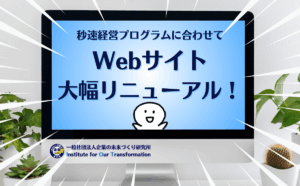「誰を選ぶか」よりも大事なこと
〜 選挙の日に考えたい、日本の停滞の根っこ 〜
■ 学力も労働力も“優秀”なのに、なぜ?
今日は参議院選挙の投票日です。
この節目に、少し立ち止まって「日本という国の今」について考えてみたいと思います。
日本はこの数十年、学力レベルは常に世界トップクラス。
教育の成果として「優秀な人材」も多く排出されてきました。
にもかかわらず、国際競争力ランキングでは、年々順位を下げ続けています。いったい、なぜでしょうか?
■ バブル崩壊からずっと低空飛行…一方、フィンランドは?
バブル崩壊以降の日本は「失われた30年」と言われるように、経済の停滞を長く引きずっています。
ところが、同じ時期に経済危機を経験した国、たとえばフィンランドはどうだったでしょう?
フィンランドは情報通信産業(ノキアなど)への大胆な産業転換や、教育・研究開発への集中的な投資によって見事に立て直し、「フィンランドの奇跡」と呼ばれるほどの復活を遂げました。
どちらも教育水準が高く、危機を経験した国。にもかかわらず、なぜここまで差がついたのでしょうか?
■ 「材料」ではなく「レシピ」が問題だったのでは?
これは、料理にたとえるとわかりやすいかもしれません。
日本は「材料(人材)」は良い。
でも、使っている「レシピ(やり方)」が、昔ながらの一択。
たとえば、火加減も見直さず、味見もせず、同じ調理法をただ繰り返す…。
これでは、どんなに素晴らしい食材を使っても、美味しい料理はできません。
政権や政党が変わったとしても、調理法(=意思決定のあり方、議論の進め方)が変わらなければ、結果も変わらないのではないでしょうか。
■ 対立ではなく「合意形成」を前提とする社会へ
私たちIOTが企業研修でお伝えしている考え方は、北欧(特にフィンランドやデンマーク)の文化にヒントを得ています。
北欧諸国では、政治でも企業でも「合意形成」や「市民参加」が当たり前のプロセスとして組み込まれています。
対立ありきの構図ではなく、異なる立場や意見を持ち寄り、対話を通じて納得解を探る。
こうしたプロセスは、単に“仲良し”になるためではなく、「信頼」と「納得感」に基づいた意思決定を可能にし、それが生産性や幸福度、国際競争力の高さに直結しています。
■ 私たちは「プロセス」にこそ目を向けたい
日本では「誰を選ぶか?」が注目されがちですが、本質はそこだけではありません。
選挙で顔ぶれが変わったとしても、その後の国会での議論が「反対のための反対」「揚げ足取り」「勝ち負け」ばかりになってしまっては、本来の目的である「良い政策を生み出す」ことにはつながりません。
だからこそ、私たちは今「対話を通じた合意形成」という“プロセスの質”そのものに目を向ける必要があると感じています。
■ IOTが目指すのは、企業から社会への波及効果
私たちIOTでは、企業の中に「合意形成の文化」を根づかせるための研修やプログラムを提供しています。
一人ひとりの社員が「当事者」として意思決定に参加し、目的に向かってベクトルを揃えていく。
これは、企業の変革にとどまらず、社会全体に対話文化を広げていく一歩だと信じています。
「誰を選ぶか」ではなく、「どうやって決めるか」。
その問いを、選挙の日に、いま一度考えてみませんか?
あなたの組織の”根っこ”を見直したい方は👉【無料Zoom相談はこちら】